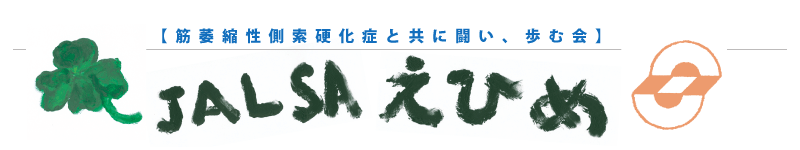1.特定医療費(指定難病)受給者証の申請手続きをしましょう
ALSと診断されたら、年齢にかかわらず「特定医療医療費(指定難病)受給者証」の交付を管轄の保健所に申請しましょう。ALSは原因不明の「指定難病」に指定されているので、特定医療費受給者証を発行してもらえば、治療費の助成を受けることができます。
特定医療費受給者証の利用
指定難病は、疾病ごとに診断基準と疾病の特性に応じた重症度分類が設定されています。
ALSでは患者さんの状態や状況をもとに、重症度を5段階(数字が大きいほど重症度が高い)で評価します。
ALSと診断され、次に該当した場合は「難病法」による医療費助成を受けることができます。
(1)重症度分類が重症度2以上
(重症度2:家事や仕事は難しいが、日常の身の回りのことはだいたいできる)
(2)軽症高額該当:重症度を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3か月以上ある場合
2.身体障害者手帳の申請をしましょう
症状が進んできたら、身体障害者手帳の交付を市町の窓口へ申請しましょう。身体障害者手帳は、障がいの程度によって1~6等級(障がいの種類別に数字が小さいほど重度)に分けられており、取得すると等級に応じた障害福祉サービスを受けることができます。
障がいが進んだら等級変更の手続きが必要です。
身体障害者手帳の利用
身体障害者手帳を取得するとさまざまなサービスが受けられます。
・医療費負担の軽減
・国税や地方税の控除または減免
・補装具購入費の助成または支給
・障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成
・公共交通機関など各種運賃や通行料の割引
・郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化
重度心身障害者医療費受給者証の申請
身体障害者手帳の交付を受け、1~2級に該当すれば、重度心身障害者医療費受給者証を取得できます。申請は市町の窓口へ行います。この証書が交付されると、病院などにおけるALSに直接関係のないかぜやけがなどの治療でも、保険診療による医療費の保険自己負担分(全額または一部)を公費で助成してもらえます。
3.障害福祉サービスの申請をしましょう
障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」に基づくサービスで、障がい者の自立支援を目的とし、利用者個別に必要な給付をする自立支援給付と市町に委ねられた地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付では介護給付、補装具給付、相談支援等を、地域生活支援事業では、日常生活用具の給付・コミュニケーション支援、移動支援などを受ける事ができます。
障害福祉サービスの利用
障害福祉サービスを利用するためには、市町にサービス利用申請をして審査・判定を受ける必要があります。市町の認定調査や医師の意見書などから、障害支援区分が認定され、区分に応じて利用できるサービスや量が決定され「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
障害支援区分とは、障がい者にとって「どれくらいの支援が必要か」を表した数字です。必要とする支援が多くなるほど区分は高くなります。(区分1~6)
自立支援給付が決まると、相談支援事業者と相談して、サービス等利用計画案を作成し市町に提出、サービスの支給決定を受け、指定障害福祉サービス事業所でのサービスが開始されます。
サービスの利用者負担は、原則として1割です。サービス量と所得に応じた仕組みになっており、定率負担、実費負担とも、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
ALSの場合、障がい程度によって、短期入所(ショートステイ)、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、重度障害者等包括支援などを利用することができます。
地域生活支援事業では、日常生活用具の給付、コミュニケーション支援、移動支援などを受ける事ができます。
重度訪問介護
常に介護が必要な障がい者に対し、入浴・排泄・食事などの介護、家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
障害支援区分4以上の方が対象です。
重度障害者包括支援
特に介護の必要度が高い障がい者に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に行います。
障害支援区分6の方が対象です。
障害支援区分の有効期間は原則3年とされていますが、ALSのような進行性の難病においては、認定の有効期間を3か月から3年の範囲で短縮することができます。障がいの進行に応じて障害支援区分の更新・変更を行います。
4.介護保険サービスの申請をしましょう
介護保険の利用は原則として65歳から(第1号被保険者)ですが、ALSの場合は16の特定疾患に含まれているため、40歳~64歳の方(第2号被保険者)も利用できます。(医療保険証が必要)
介護保険の利用
介護保険を利用するには、市町へ要介護(要支援)認定の申請を行います。認定調査と医師の意見書から介護区分が審査され、介護の度合いに応じたサービスを受けるための指標となります。
要介護度:要支援1~2、要介護1~5(要介護5が最も重い)に区分されます。
認定通知後、介護保険によるサービスを受けるためには、どの介護保険サービスを受けるかを選んでケアプランを作成しなければなりません。自分で作成できない場合は、介護支援事業者やケアマネジャーに依頼してください。
作成したケアプランを市町の担当窓口に届け出た後、自分で選んだ介護サービス事業者と契約を交わします。介護保険の利用限度内でサービスを受けたら、利用者は利用額の1~3割(所得金額に応じ)を負担します。(残りは介護保険料と自治体が負担)
なお、第2号被保険者は1割負担です。
利用限度額を超えて利用する場合は、全額自己負担になります。また、介護保険を利用中も介護保険料は支払う必要があります。
介護保険サービスの種類
介護保険サービスには、訪問サービス、通所サービス、施設入居サービス、福祉用具の購入・レンタル、住宅リフォーム等があります。
訪問サービス:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ等
通所サービス:通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス:短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
その他のサービス:福祉用具貸与(車椅子・介護ベッド)、特定福祉用具購入補助(入浴や排泄などに使う福祉用具)、居宅介護住宅改修費補助(バリヤフリー、手すり設置、浴室等の床の滑り止め、洋式便器への取り替え等)
5.その他の支援・補助など
上記以外にも、ALSの症状が重くなったらさまざまな支援制度があります。各種制度は地方自治体によって異なりますので、 各都道府県・市町の福祉窓口や保健所に問い合わせてくだい。
また、生命保険では、高度障害が認められた場合保険金を受け取ることができます。
○特別障害者手当(要介護4・5)
○生活資金の貸付、生活保護受給など
○重度障害者入院時コミュニケーション支援
○レスパイト入院(在宅療養の患者が一時的に入院することによって、介護する家族の方が介護から離れて、リフレッシュするための介護サービス。医療保険制度適用)
******************************************************
不安や悩みを抱えた時は近くに相談できるところを見つけましょう。保健所や難病相談支援センター、病院のソーシャルワーカー、ケアマネージャー等。
また、日本ALS協会(都道府県支部)には先輩患者・家族がたくさんいます。不安や疑問を話すことで療養生活の参考となるばかりでなく、悩んでいるのは自分ばかりでないことを実感でき、ALS患者の孤立感からも開放されます。
患者自身がどのように暮らしたいかを考えておくことが最も重要です。それが決まっていないと、周囲の人は何をどう支援すればいいのか困惑します。ALSはさまざまな制度を利用できる疾患です。この先、自分が病気と付き合いながら、どのような生活を送りたいのか考えて、制度をうまく活用しましょう。病気だからと諦めるのではなく、自身の目的をもって前向きな療養生活を送りましょう。